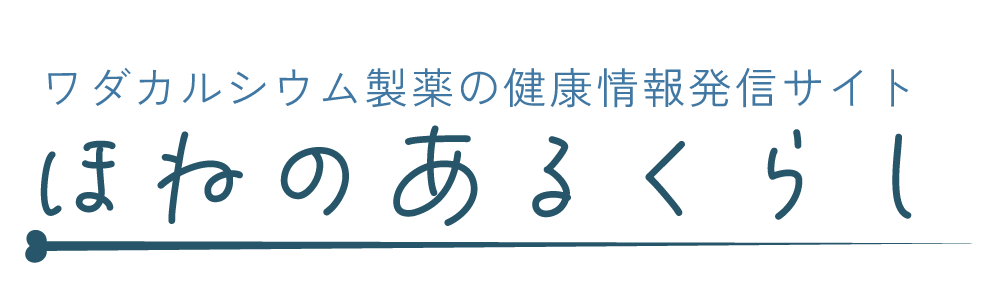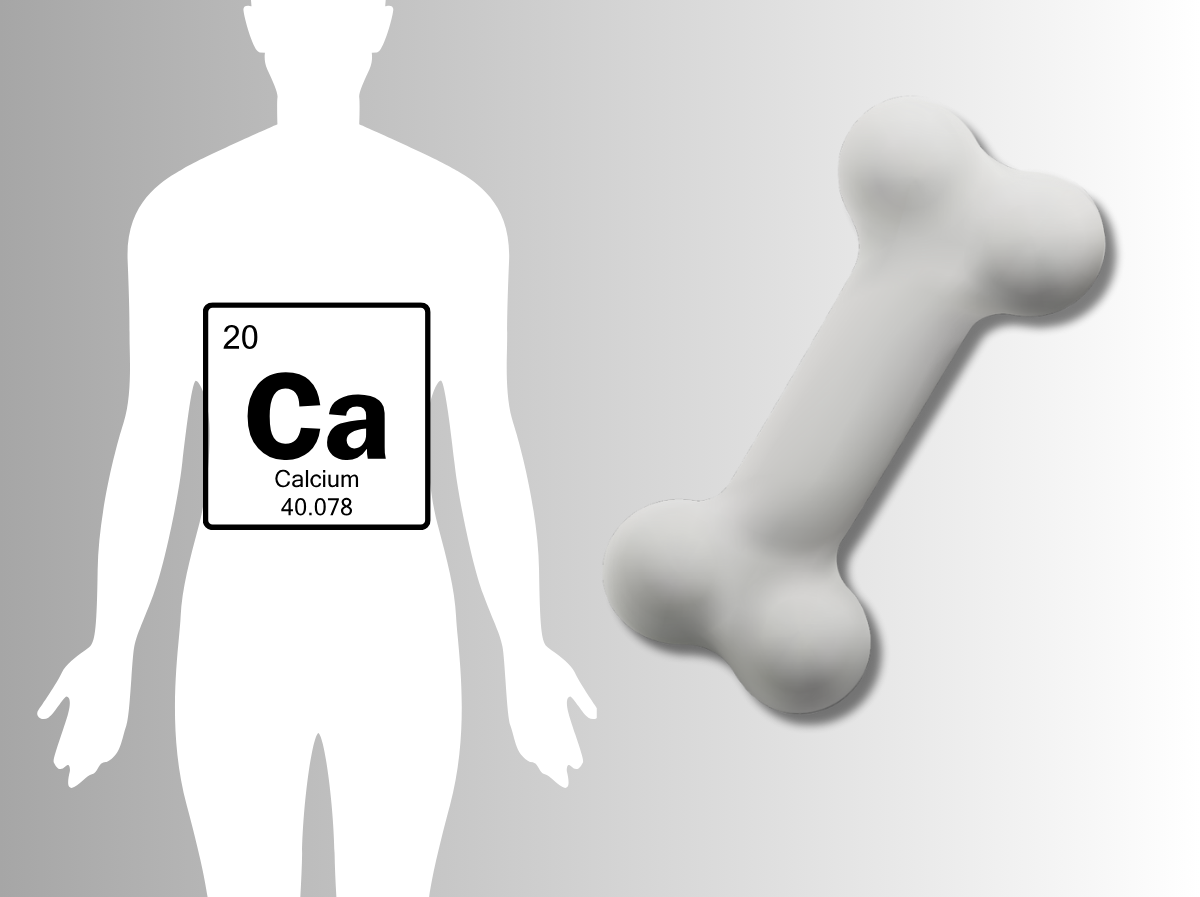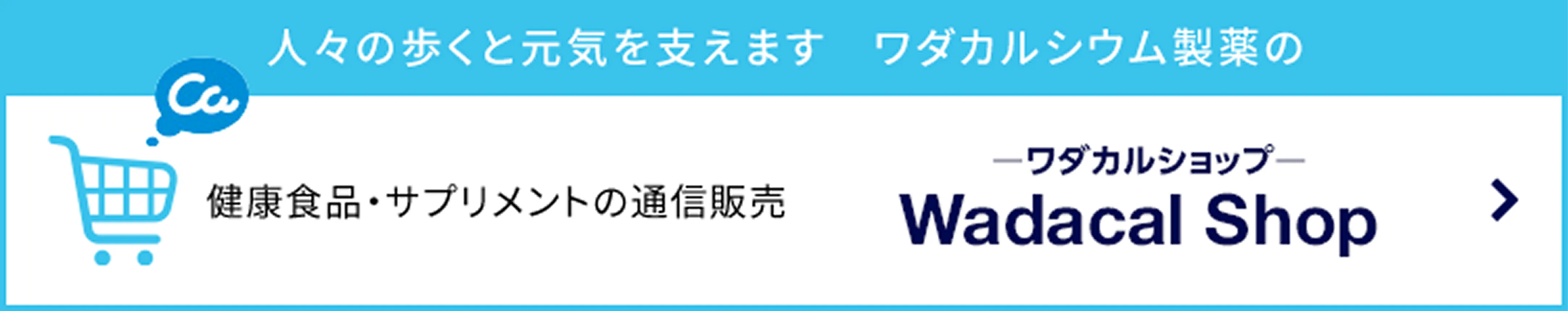この記事の執筆:田中 清(静岡県立総合病院 医長)
経歴:
京都大学で助手として研究に従事した後、甲子園大学、京都女子大学、神戸学院大学で栄養学と食生活学、内分泌・代謝学の教育・研究に携わる。現在は静岡県立総合病院 臨床研究部長として、臨床と研究の両面から地域医療と健康寿命の向上に取り組んでいる。
続きを読む
■所属学会・資格
日本内科学会認定医
日本骨粗鬆症学会認定医
病態栄養専門医
■研究
骨粗鬆症性骨折・再骨折の予防における脂溶性ビタミンの意義に関する研究
ビタミンB12不足の臨床栄養学的意義に関する研究
ビタミン不足の臨床的・社会的意義に関する研究
カルシウムの役割

カルシウムは、2つの重要な役割を果たします。
1つは骨の硬さを維持し、体を支えることですが、もう1つは「生命を維持する」という役割です。
体内にはおおよそ1㎏のカルシウムがありますが、その99%が骨と歯にあります。
それ以外にあるのはわずか1%で、その1%がまた偏った分布を示します。
細胞内のカルシウム濃度はふだん、細胞外のわずか1万分の1と非常に低いため、
細胞外から細胞内にカルシウムが流入すると細胞が興奮し、
神経の情報伝達や筋肉の収縮などが起こります。
したがって、細胞外・血液中カルシウム濃度を正常に保つことは生命維持に欠かせません。
骨におけるカルシウムの役割

人間の骨は2つの大事な役割を果たしています。
1つの役割はもちろん硬い骨として体を支えることですが、もう1つの役割はカルシウム貯蔵庫です。
血液中カルシウム濃度が低下すると、生命が保てませんので、何としても正常に維持する必要があります。
海にすむ生物は、必要時いつでもカルシウムの豊富な海水からカルシウムを取り込めますので、
カルシウム不足にはなりません。
しかし上陸した時点で、陸上生物は常にカルシウム不足の危険と隣り合わせになりました。
このためカルシウム貯蔵庫としての骨ができたと考えられています。
エビやカニの甲羅は硬いだけですが、
人間の骨は硬い組織として体を支えるとともに、カルシウム貯蔵庫の役割をも果たしています。
なぜカルシウムをしっかり摂らないといけないのか?

血液中カルシウムを、財布の中の手持ちの現金とすると、骨のカルシウムは、カルシウム銀行の預金残高です。
手持ちの現金が乏しくなると預金を引き出すのと同じように、血液中カルシウムが低下しそうになると、骨のカルシウム銀行の預金を引き出します。
具体的には、骨を壊し、骨に蓄えられていたカルシウムを血液に移動させることにより、
血液中カルシウム濃度を保ちます。
血液中カルシウム濃度は、正常範囲を維持できるように厳密に調節されていますので、
カルシウム不足の食事を続けても、血液中カルシウム濃度は低下しませんが、
骨が犠牲になってどんどん減っていきます。
十分量のカルシウムを摂取することは、骨の健康維持に欠かせません。
カルシウム摂取は足りているのでしょうか?

厚生労働省では毎年、国民健康・栄養調査を行っています。
性・年齢別に、いろんな栄養素をどの程度摂っているのか調査するものです。
2017年の結果によると、年代により若干異なりますが、
50歳以上の男性で1日平均484~584mg、女性で511~582mgです。
各栄養素をどれくらい摂れば良いのかは、
日本人の食事摂取基準に示されており、2015年版によると、
カルシウムの推奨量は、50歳以上の男性で700mg、女性で650mgなので、男女とも足りていません。
国民・健康調査は毎年行われていますが、カルシウム摂取量は全く増えておらず、
平均値が推奨量に達したことがありません。
カルシウムは骨の健康維持に欠かせないにも関わらず、非常に摂りにくい栄養素なのです。
どんな食品を摂れば良いのですか?

どんな食品にでも、ある程度以上の量が含まれている栄養素もありますが、
カルシウムの豊富な食品は、かなり限られています。
しかもカルシウムの吸収率は食品ごとにかなり異なっています。
上西一弘先生(女子栄養大学)が、
非常に厳密な方法で調べられた結果によると、
カルシウム吸収率は、牛乳で約40%、小魚で約33%、野菜で19%でした。
これはカルシウムが決まった量含まれている食事を、
一定期間摂ってもらい、血液検査だけではなく、
尿や便中のカルシウムの量も測定するという方法で研究されたもので、非常に信頼性が高いです。
カルシウムを食品から摂取するのであれば、吸収率を考えて、
まずは乳製品、次いで小魚ということになりそうです。
カルシウムを摂りすぎることはないのですか?

どの栄養素でも、不足・過剰とも良くないのは当然です。
日本人の食事摂取基準2015年版において、耐容上限量という目安が定められています。
これ以上摂ると健康障害の危険性があり、ここまでは近づかない方が良いという量で、男女とも成人では1日カルシウム摂取量2,500mgです。
牛乳に換算すると1日2リットル以上ですから、毎日こんなに牛乳を飲める人はいません。
実際にカルシウムを摂り過ぎて、高カルシウム血症(血液中カルシウム濃度が上がりすぎる)が起こった例は、
1日3,000mg以上に限られており、安全を見越して2,500mgとしたものです。
カルシウムは、日本人の多くが不足している栄養素なので、過剰の心配をするより、積極的摂取を心がけるべき状況です。
カルシウム吸収を助けるビタミンD
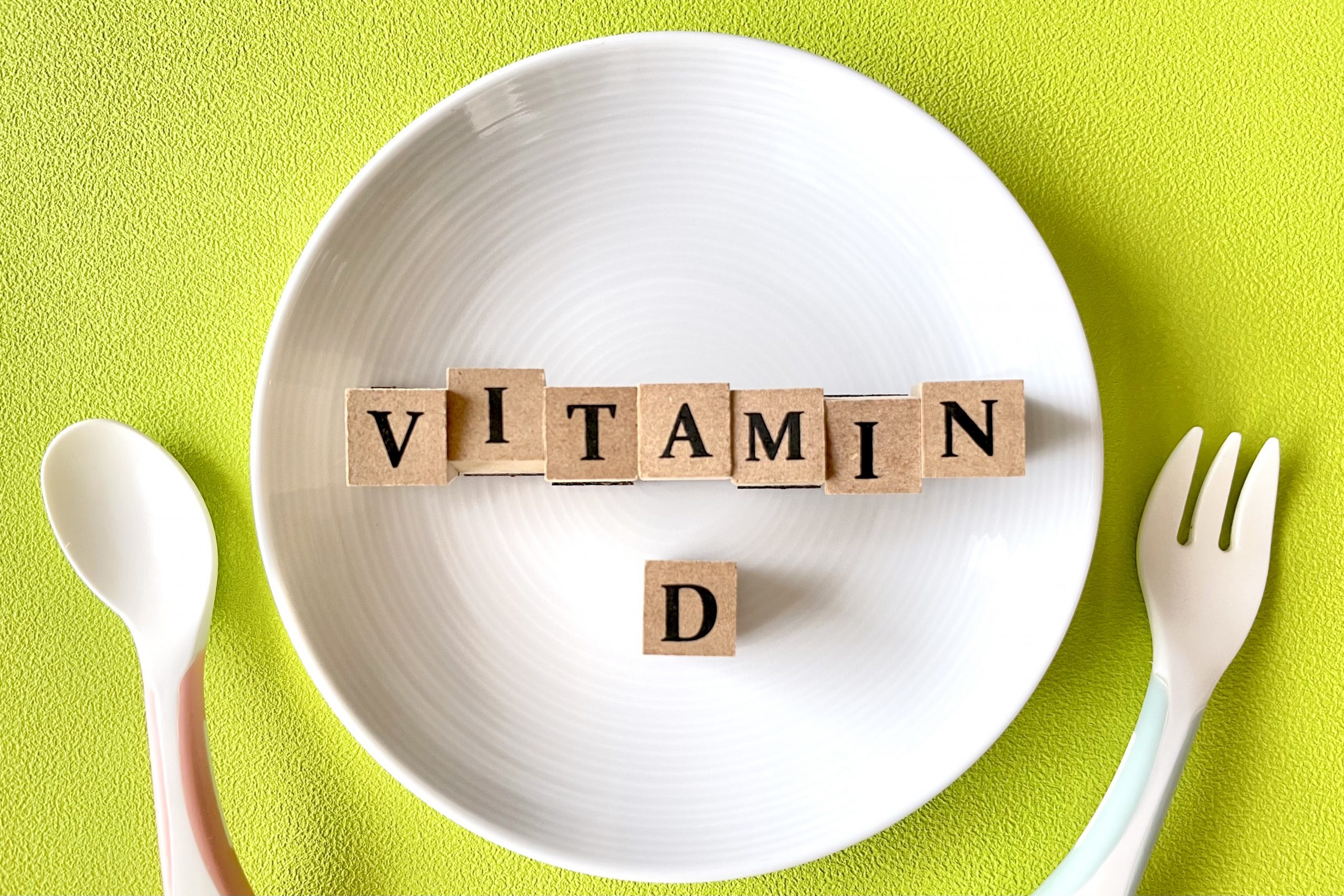
カルシウムの重要性はよくご存じかと思いますが、
ビタミンDはカルシウムを助ける大切な栄養素です。
ビタミンDは体の中で、多くの大事な仕事をしていますが、
最も重要なのは、カルシウムの腸からの吸収を助けることです。
骨はビルに例えられます。
鉄筋の枠組み+コンクリートでビルができるように、
骨はコラーゲンを中心としたタンパク質の枠組みの上に、
リン酸カルシウムが沈着してできます。ビタミンDが欠乏すると、
せっかく摂ったカルシウムが十分吸収できず、カルシウムが沈着できません。
これが子どもの時に起こったのをクル病、成人で起こったのを骨軟化症といいます。
ビタミンD充足のために

本来ビタミンは体内で合成できず、食事から摂取すべき栄養素なのですが、
ビタミンDは紫外線があたると皮膚でかなりの量ができます。
白人ができたのはビタミンDのせいだという説があります。
アフリカで誕生した人類が高緯度地域に住むようになると日照量が減り、
ビタミンDが十分できなくなるので、皮膚の奥まで紫外線が届くように、メラニン色素が減少したというのです。
最近世界的にビタミンD不足者の割合が非常に高く、あまりに紫外線を悪者にして、
日照を避けすぎたのが、原因の1つと考えられています。
もちろん真っ黒に日焼けする必要はありませんが、カルシウムを十分摂った上で、適度の屋外活動をすることは、骨の健康維持に重要です。
骨におけるカルシウムの役割

日本人のカルシウム摂取は不足していることをお話しましたが、
もう少し詳しく見ると、平成29年度国民健康栄養調査によると、
カルシウム摂取量は、7~14歳で1日673mgですが、15~19歳で495mg、20~29歳で495mgと減少しています。
将来のために丈夫な骨を作っておくべき時期に困ったことです。
7~14歳でのカルシウム摂取量が比較的多いのは、
おそらく学校給食で牛乳が提供されるためだと考えられます。
牛乳200mLで約200mgのカルシウムが供給され、
小魚や野菜のカルシウムに比べて、牛乳のカルシウムは吸収率が高いです。
給食に和食を取り入れるのは良いのですが、和食に合わないからと、
給食から牛乳を外す動きが一部にあり、骨の健康を考えると気になる話です。
リンの摂りすぎにご注意

骨はタンパク質の枠組みの上に、リン酸カルシウムが沈着してできます。
リンはカルシウムとともに骨に欠かせない材料であり、その他にも、エネルギー代謝に関わり、重要な役割を果たしていますが、摂りすぎに注意しないといけないミネラルでもあります。
リンを摂りすぎるとカルシウムの吸収が阻害され、また腎臓に対して有害です。
厚生労働省の国民健康・栄養調査結果を見ると、リンの摂取量は一見問題ないのですが、大きな落とし穴があります。
加工食品において、リンは食品添加物として広く用いられており、気づかないうちに、リンの取り過ぎになっている可能性が高いのです。
加工食品を取り過ぎないことも、骨の健康維持に重要なことです。
なぜ骨の健康が大事なのでしょうか?

骨粗鬆症は、骨が脆くなり、骨折しやすくなった状態です。
ご注意頂きたいのは、骨折しやすくなった状態であり、骨折したものではないことで、危険性が増していれば、折れていなくても、予防・治療対象だということです。
血圧やコレステロールが高いと心筋梗塞や脳卒中の危険性が高まるので、予防・治療するのと同様、骨粗鬆症は生活習慣病的な病気です。
だから運動や、カルシウム摂取など栄養面が重視されます。
骨粗鬆症の薬を飲んでいるので、今さらカルシウムなんてと思われる方もあるかもしれません。
しかし骨粗鬆症治療薬新薬はすべて、カルシウム・ビタミンDの充足が前提になっており、そんな方にとっても、十分のカルシウムは不可欠です。
カルシウム摂取以外にどんな注意が必要でしょうか?

骨はたんぱく質でできた枠組みの上に、カルシウムが沈着しています。
全般的低栄養状態や、たんぱく質摂取不足状態で、カルシウムだけたくさん摂っても、十分の効果は得られません。
筋肉でのたんぱく質合成能力は、年齢とともに低下しますので、高齢者では若い人以上のたんぱく質摂取が必要と言われています。
年を取ったらあっさりしたものが良いだろうと考えすぎるのは、問題があり、一定量の良質のたんぱく質は摂らなければいけません。
また運動に伴う筋肉の収縮は、骨表面の骨膜を刺激し、骨形成(骨を作る)を促進する合図になります。
たんぱく質を摂り、適度に運動をした上で、カルシウムを補充することが、骨の健康のために非常に有効です。

この記事の執筆:田中 清(静岡県立総合病院 医長)
経歴:
京都大学で助手として研究に従事した後、甲子園大学、京都女子大学、神戸学院大学で栄養学と食生活学、内分泌・代謝学の教育・研究に携わる。現在は静岡県立総合病院 臨床研究部長として、臨床と研究の両面から地域医療と健康寿命の向上に取り組んでいる。
続きを読む
■所属学会・資格
日本内科学会認定医
日本骨粗鬆症学会認定医
病態栄養専門医
■研究
骨粗鬆症性骨折・再骨折の予防における脂溶性ビタミンの意義に関する研究
ビタミンB12不足の臨床栄養学的意義に関する研究
ビタミン不足の臨床的・社会的意義に関する研究