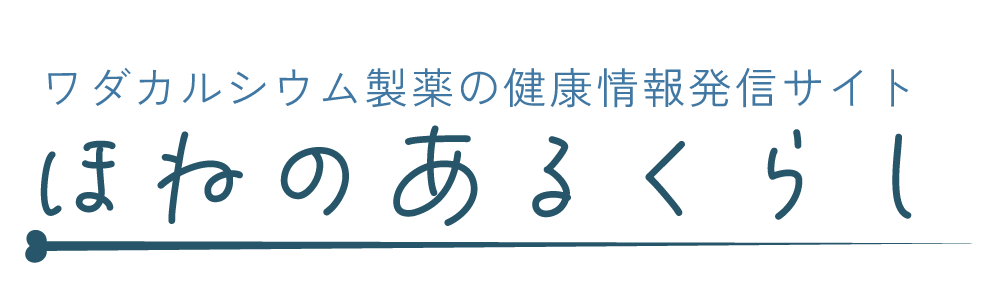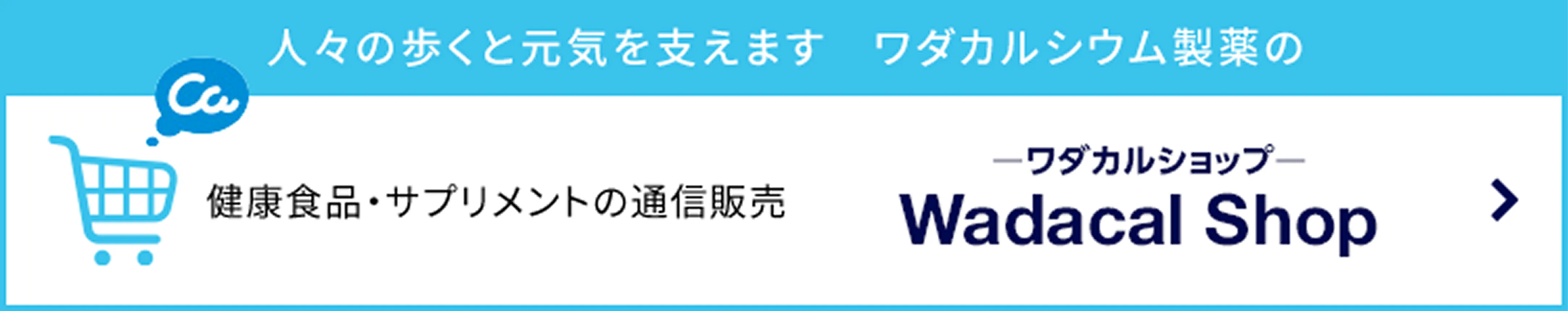膝の痛みが気になり始め、食生活で対策できないか考える方も多いのではないでしょうか。
膝の痛みは、運動やマッサージの他、食生活を見直しながら膝に良い食べ物も摂取するといった予防策が大切です。
今回は膝に良い食べ物や食品の選び方、摂取する際に注意すべきポイントをわかりやすく紹介します。
最近、膝の痛みが気になり始めた方は参考にしてみてください。

この記事の監修者:長田 夏哉(整形外科・リハビリテーション科・一般内科)
経歴:
日本医科大学卒業後、慶應義塾大学整形外科学教室に入局し、慶應義塾大学病院や済生会神奈川県病院、川崎市立川崎病院などで経験を積む。平成17年に同病院の医長を務め、同年9月「田園調布 長田整形外科」を開設。現在は整形外科専門医・スポーツドクターとして地域医療とスポーツ分野に幅広く取り組んでいる。
続きを読む
■所属学会・資格
日本整形外科学会 専門医
日本整形外科学会認定 スポーツ医
日本スポーツ協会公認 スポーツドクター
日本整形外科学会
日本整形外科スポーツ学会
日本臨床スポーツ医学会
日本手の外科学会
日本運動器科学会
日本骨粗鬆症学会
■所属・関連協会
一般社団法人 日本スポーツビジョン協会 理事長
一般社団法人 国政生命意識協会 顧問
一般社団法人 MCA学会 理事
一般社団法人 手のひらセルフケア協会
サウンドヒーリング協会 アドバイザリーブレイン
NPO法人 予防医学療法研究会 顧問
認定NPO法人 日本YOGA連盟 アドバイザー
変形性膝関節症予防および膝に良い食べ物は?

加齢とともに膝が痛み始めた場合、変形性膝関節症の可能性があります。
痛みを悪化させないよう早めに予防策を講じましょう。
記事の後半で詳しく解説しますが、変形性膝関節症は膝の軟骨がすり減ることで痛みを感じます。膝の軟骨は一度すり減ると戻すことは困難です。
膝の軟骨がすり減らないようにするには、日々の運動やストレッチのほか、栄養バランスのとれた食事を心がけていく必要があるのです。
まずは、膝に良い食べ物と栄養素についてわかりやすく紹介していきます。
タンパク質
五大栄養素(および三大栄養素)のひとつでもあるタンパク質は、アミノ酸に分解されて皮膚や内臓、骨、筋肉を形作ります。
後述しますが、膝の痛みを予防するなら骨だけでなく筋肉の強化が欠かせません。
膝の骨や筋肉を丈夫に保つためには、タンパク質の含まれる食べ物を継続的に摂取するのが大切です。
以下にタンパク質が含まれている主な食べ物を紹介します。
- 納豆や豆腐といった大豆製品
- 卵
- 鶏のささみ、むね肉
タ ンパク質が含まれる食べ物を摂取する際は、動物性か植物性かにも注目しましょう。
動物性タンパク質は肉や魚介類などにあるタンパク質で、必須アミノ酸の中でもロイシン(筋肉の合成にかかわる)を多く含んでいます。
必須アミノ酸は体内で作れず、なおかつ日々摂取しなければいけない栄養素です。
一方、植物性タンパク質は大豆製品など植物性の食べ物に含まれていて、動物性タンパク質より脂肪燃焼効果を期待できます。
カルシウム
膝の骨を強くするには、適度なカルシウムの摂取も欠かせません。
カルシウムは臓器や歯・骨に存在するミネラルで、加齢による骨量の減少を抑える上でも重要です。以下にカルシウムが含まれている主な食べ物を紹介します。
- 牛乳
- チーズ
- ひじき
- モロヘイヤ
なお、カルシウムの吸収率は食べ物によって異なるため、吸収率の高いチーズといった乳製品を中心に摂取しても良いでしょう。
マグネシウムやビタミンD・Kを含む食べ物と一緒に食べるのもポイントです。
ビタミンD
ビタミンDはカルシウムの吸収を高めてくれるだけでなく、骨の形成や成長のサポートも行ってくれます。
日光を浴びると体内から生成できますが、食べ物からも摂取できます。
以下にビタミンDが含まれている主な食べ物を紹介します。
- サンマやいわしなどの魚類や魚卵
- 干しシイタケなどのキノコ類
- 卵黄
ビタミンDは、水に溶けにくく油に溶けやすい脂溶性ビタミンで、熱に強い特長を持っています。
そのため、加熱調理してもビタミンDを摂取することが可能です。
ビタミンK
ビタミンKは骨吸収を抑制してくれる栄養素で、脂溶性ビタミンでもあります。葉野菜にはビタミンKが多く含まれている傾向です。
以下にビタミンKが含まれている主な食べ物を紹介します。
- ブロッコリー
- 小松菜
- ほうれん草
- 海苔
- わかめ
- モロヘイヤ
納豆やモロヘイヤなどはカルシウムとビタミンKを含んでいるので、1つの食べ物からまとめて栄養素を摂取することが可能です。
マグネシウム
マグネシウムは、血圧の調整やタンパク質の合成、骨を強化させる上で欠かせない栄養素です。骨を構成する成分にはマグネシウムも含まれているので、カルシウムとともに摂取しましょう。
以下にマグネシウムが含まれている主な食べ物を紹介します。
- アーモンド、ピーナッツなどのナッツ類
- ほうれん草
- 納豆をはじめとした大豆製品
- 玄米
カルシウムを摂取しすぎるとマグネシウムの排出量が増えてしまうため、カルシウム2:マグネシウム1の比率で摂取するよう心がけるのも大切です。
食生活を見直す上で注意すべきポイント

食生活の改善を図るには、膝に良い食べ物を取り入れるだけでなく、アルコールや間食などに関する注意点についても把握しておく必要があります。
それでは、食生活を見直す上で注意すべきポイントを1つずつ確認していきましょう。
膝に悪い食べ物や食べ方を避ける
食事の改善を図りたいときは、膝に悪い食べ物を避けるのが大切です。たとえば、高カロリーの食べ物や塩分の摂りすぎには気を付けましょう。
高カロリーな食べ物を食べすぎない
体重が増えると膝の痛みが生じるケースがあります。高カロリーな食べ物は、体重の増加につながりますし、栄養バランスが偏ってしまいます。
とくに外食の頻度が高い方やファストフードをよく食べる方は、野菜や膝に良い食べ物をバランスよく取り入れた食事へ切り替えましょう。
なお、食事の回数や量を大幅に減らすといった方法は、場合によって栄養不足による筋力低下などのリスクが懸念されます。基礎代謝が低下し、減量しにくい体質へ変わってしまう可能性もあるので、栄養バランスを意識しながら普段通りの食事回数や適度な食事量を保つのも大切です。
塩分を摂取しすぎないようにする
とくに濃い味が好きな方は、塩分を摂りすぎないよう食生活を見直してみるのも大切です。
塩分を摂りすぎると、塩分に含まれるナトリウムの排出時に骨にとって重要な栄養素であるカルシウムが排出されてしまいます。また高血圧のリスクなど、生活習慣病といった点でも注意が必要です。
たとえば、薄味の味付けに変えたり減塩調味料を活用したりしてみるのが、塩分の摂りすぎを防ぐ方法のひとつです。どうしても塩分を減らすのが難しい方は、味噌汁をいつもの半分の量で飲むなど、摂取カロリーや栄養素にそれほど影響が大きくない、塩分が高いものを調整してみると取り組みやすいです。塩分を摂りすぎてしまったときは、水分を多めに補給したり適度な運動で塩分を排出したりしてみましょう。
アルコールや間食の頻度を減らす
お酒が好きな方や間食の習慣が身に付いている方は、なるべく頻度を抑えてみましょう。
アルコールの摂取は、軟骨の弾力性を低下させて摩耗させやすくする可能性があるので、膝の痛み予防という点で注意すべき成分です。また、タバコにも同様のリスクがあります。
間食の習慣は肥満につながるため、少しずつ回数や量を減らしていく必要があります。
満腹中枢が働くように食べる
食事の際は、満腹中枢の働きやすい食べ方を意識するのが大切です。
満腹中枢とは、食欲を抑制させる中枢神経のことです。食事によって血中の血糖値が上昇すると、満腹中枢の働きによって満腹感を覚えます。
満腹感を覚え始めるのは、食事を始めてから約15~20分後です。そのため、とくに食べるのが速い方は、ゆっくりと食事するように意識したり、噛む回数を増やしたりしましょう。食事量を抑えやすくなる可能性があります。
膝の痛みは主に何が原因?

膝の痛みを予防するために摂取したい栄養素は、なぜ必要なのでしょうか。痛みの予防と栄養のかかわりを理解するには、痛みの原因を知る必要があります。
膝の痛みにおいて考えられる原因は非常に多く、加齢によって引き起こされるケースもあります。膝の痛みが起こる主な原因についてそれぞれわかりやすく解説します。
膝の軟骨がすり減る(変形性膝関節症)
クッションの役割を持つ膝の軟骨がすり減ると、衝撃を受け止めきれず痛みを感じます。そして変形性膝関節症の発症につながります。変形性膝関節症の痛みは、膝の曲げ伸ばしや階段の昇り降りの際に現れます。
また、軟骨のすり減った状態で膝関節を動かしていると、削られたり、痛みにつながります。
骨の変形を招いたり膝に水が溜まったりといった症状も出てくるため、日常生活に支障をきたすリスクもある症状です。一般的に60代以降の方が発症しやすい傾向ですが、40・50代から発症する方も見られます。
関節リウマチ
関節リウマチを発症した場合、膝を含むさまざまな関節が痛んだり腫れたりしてしまいます。
免疫機能に異常が発生すると自分自身の細胞を攻撃してしまうため、関節の炎症および関節リウマチの発症につながります。しかし、免疫機能の異常に関するメカニズムは現在完全には解明されていません。
発症から初期の段階では、主に手足の指にある関節から痛み始め、症状の進行とともに膝関節や股関節などさまざまな箇所の炎症、麻痺を引き起こします。関節リウマチは食事で改善・予防することはできませんが、関節への負担を増やさないように体重を増やしやすい食事は避けた方が良いとされます。
半月板損傷
半月板損傷の場合、膝の痛みや腫れ、膝の可動が制限される「ロッキング」といった症状も生じます。
膝関節の内側と外側には、三日月形状の半月板という組織があります。主に衝撃を和らげるクッションの働きを担っている組織です。
半月板損傷の主な原因は、事故やスポーツで強い衝撃を受けたり、加齢によって半月板が変形したりすることです。また、慢性化してしまうと変形性膝関節症を発症する場合があるので、注意の必要な疾患のひとつといえます。リハビリ時に筋力の強化も必要となりますので、食事の面では本記事で紹介したような内容を意識すると良いでしょう。
リンパ節の循環不良
膝の裏側から痛みを感じたり腫れていたりする場合は、リンパ節の循環不良が原因の場合もあります。リンパ管は体内に溜まった老廃物を排出する器官で、とくに太いリンパ管をリンパ節と呼びます。膝の裏側にはリンパ節があるので、リンパの循環不良による影響を受けてしまいます。
運動不足や栄養バランスの偏った食生活、肥満などが、膝裏にリンパ節の詰まる主な原因とされています。また、長時間同じ姿勢を続けると、リンパの循環不良につながります。
中高年に多い変形性膝関節症はなぜ起きる?

膝の痛みにかかわる原因をいくつか紹介しましたが、多くの場合は変形性膝関節症がかかわっています。膝に関する疾患の中でも変形性膝関節症は、40~50代から発症し始める疾患のひとつです。予防するためには、膝に良い食べ物を知るだけでなく、なぜ発症するのかという点も知る必要があります。
ここからは、中高年に多い変形性膝関節症が起きる原因について紹介します。
軟骨の老化
変形性膝関節症の主な原因は、関節軟骨の老化です。
膝関節の軟骨は、膝の使いすぎだけでなく老化によってもすり減っていきます。また、老化に伴い軟骨の弾力性が低下していくため、クッションとしての機能も失われやすいです。とくに膝の状態が気になる中高年の方は、膝に良い食べ物を摂取し、栄養バランスに気を付けるのも大切です。
食生活の乱れなどによる肥満
肥満体型を放置していると膝関節に大きな負担をかけてしまい、変形性膝関節症の発症リスクを高める可能性があります。
歩行時や立ち上がる際、膝関節には体重の2~3倍程度の負荷がかかっています。そのため、肥満体型の方は、減量に向けて食事量の見直しが必要です。
運動不足による筋力低下
運動不足の続く生活を送っている場合は、変形性膝関節症のリスクに気を付けるのが大切です。
運動の習慣がないと、膝周辺を含む脚の筋力低下を招きます。筋力の低下している状態で歩いたり立ち上がったりといった動作を繰り返すと、膝関節にかかる負荷を筋力でサポートできず、変形性膝関節症を引き起こしてしまう可能性があります。
最近運動していない40~50代の方は、運動不足に陥っていないかどうか日々の生活を見直してみましょう。
遺伝
変形性膝関節症は、老化や運動不足といった要素の他、遺伝も関係している場合があります。「DVWA」という遺伝子が変形性膝関節症に関係していて、発症リスクを高めているとされています。
外部からの強い衝撃(外傷含む)や後遺症
膝に負担のかかる仕事をしている場合や交通事故などによる強い衝撃を受けた場合にも、変形性膝関節症を引き起こす可能性があります。
たとえば、重量物を運ぶ、しゃがみ続けて作業を行う、長時間立ちっぱなしの作業といった行為は、膝に大きな負担を与えます。また、事故などによる半月板損傷や脱臼といった症状が、変形性膝関節症につながることもあります。化膿性関節炎といった感染症の後遺症が原因で、変形性膝関節症を発症するケースも存在します。
膝の軟骨がすり減らないようにするには?

変形性膝関節症の原因でもある膝の軟骨をすり減らさないための対策として、運動と可動域の改善、栄養バランスの整った食事が挙げられます。それぞれの対策について解説します。
筋力が低下しないよう膝まわりの筋肉を鍛える
膝や脚全体の筋力が低下しないよう、運動を習慣化させるのも膝の痛み予防として欠かせません。
前段でも触れたように変形性膝関節症の原因には、運動不足も含まれています。そのため、膝関節を筋肉で支えられるよう、太ももや脚全体のトレーニングを取り入れるのが大切です。
以下に脚を鍛えられるトレーニング方法をいくつか紹介します。
| 脚全体を鍛えるスクワット | 肩幅より少し広い間隔で立ち、腰をゆっくり下ろす
・膝が90度に曲がらないよう気を付ける ・膝を伸ばすときもゆっくり行う |
| 太ももを鍛える | 椅子やベッドなどの手前に座り、太ももが椅子にあまり付かないようにする。片足ずつゆっくり上げ下げする(バランスが不安な場合は軽くつかまりながら)
・片足を地面から水平もしくは1cm上げたら5~10秒程度待機 ・20回程度上げ下げしたあとは、反対の足も同様に行う |
| 太ももの外側を鍛える | 横向きに寝た状態で、そのまま片足を天井に向かってゆっくり上げたら5秒程度待機。 同じ動作を10回程度繰り返す(もう片方の足も同様の動作で鍛える) |
膝周辺を鍛えるときに注意すべきポイントは、無理のない範囲でゆっくり動くという点です。ただしすでに治療を開始している場合は無理に動かすと悪化する恐れもあります。とくにスクワットなどは負担が大きい動きです。治療中の方や、痛みがひどい方などは、まずは医師に相談してください。
ストレッチやマッサージで膝の可動をよくする
筋力の低下している状態で急に運動を始めると膝の痛みやケガにつながる可能性もあるので、運動の前にストレッチやマッサージで膝の可動域を改善しておきましょう。
太もも周辺の柔軟性を高めたい場合は、仰向けの状態で片足を身体に引き寄せる形で曲げて、10秒程度そのままの状態で止まります。あとは、反対の足も同様の動きを繰り返します。
膝の動きを改善したいときは、床で脚を前に伸ばした状態でかかとあたりにタオルなどの布を敷きます。準備ができたらゆっくりと体操座りの形へ膝を曲げたり、伸ばしたりを繰り返します。
ただし、いずれのストレッチも膝に痛みを感じるときは、医師に相談した上でどのような運動療法を取り入れるべきか確認するのが大切です。
肥満による膝への負担を避けるために食生活を見直す
肥満は膝への負荷を増やす原因のひとつなので、食生活を見直して適正体重への減量に励む必要があります。
ただし、体重を落とすだけでは膝周辺の筋力低下につながり、かえって膝の痛みを招いたりケガのリスクを高めたりしてしまう可能性もあります。減量を検討する際は、ストレッチと運動による膝周辺の筋力向上も図るのが大切です。
まとめ
膝に良い食べ物は、主にタンパク質やカルシウム、マグネシウム、ビタミンD・Kといったいずれか1つ以上の栄養素を含むものを指しています。また、膝の痛みを予防するには、膝に悪い食べ物や食べ方をしないよう気を付けたり適度な運動やストレッチを取り入れたりするのも大切です。
最近、膝が痛くて悩んでいる方や膝の腫れなどの症状に気付いた方は、早めに病院を受診し、適切な治療を進めてもらいましょう。